3月
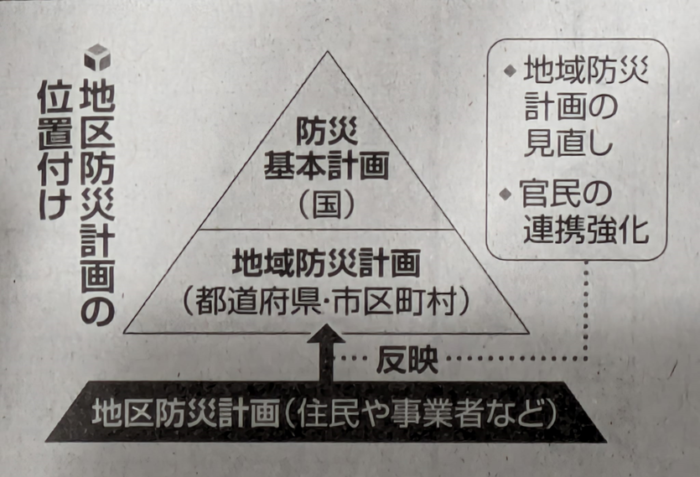
3.11 東日本大震災から13年(その1)~地域住民が作る「戦闘計画」と、地方自治体が作る「作戦計画」の連携が不可欠~(6.3.11)
いつの間にか東日本大震災から13年間が経った。 この間、防災への理解、特に災害への直接的な対処への関心が高くなり、自助への理解が広まったが、これは主として個人の行う防災対策で、準備がなければ自分自身がひどい目にあうことを […]
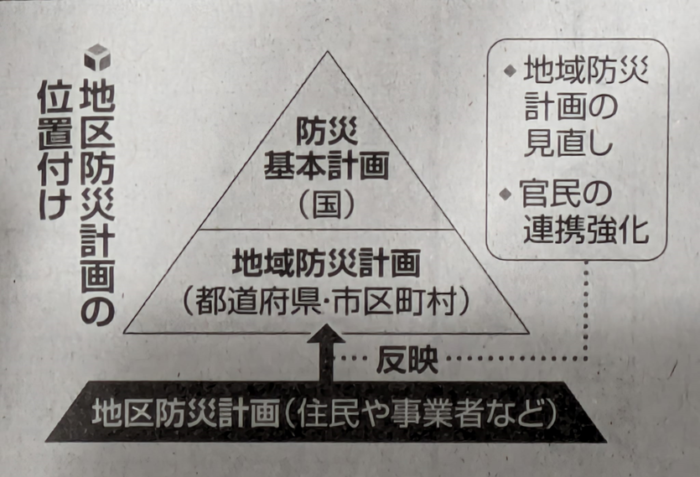
いつの間にか東日本大震災から13年間が経った。 この間、防災への理解、特に災害への直接的な対処への関心が高くなり、自助への理解が広まったが、これは主として個人の行う防災対策で、準備がなければ自分自身がひどい目にあうことを […]
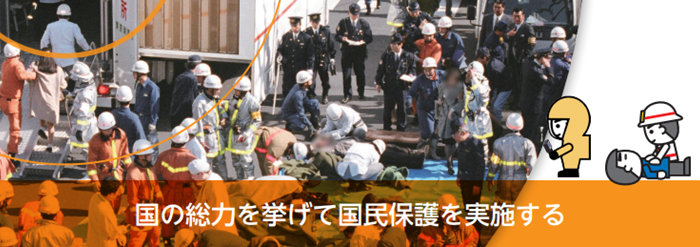
■国民の生命財産の保護の責任 消防は、近隣自治体間の協力体制として「組合消防」を組織することにより、効率的な運用を目指してきた。 その結果、約1000の基礎自治体は消防本部を直接指揮することがなくなった。 地方自治の根幹 […]

■総務省消防庁 「総務省消防庁」は消防組織法上に位置づけられた組織で、消防に関する制度の企画及び立案、広域的に対応する必要のある事務などを任務としていて、消防関係法令の改正管理、緊急消防援助隊・国際救助隊といった広域部隊 […]

【つるみ共育保育園園長で、防災への取り組みをなさっている藤實智子さんに、保育園での防災意識の現状などについて伺いました。藤實さんは、東京消防庁で消防士の経験があり、一般社団法人保育の寺子屋代表理事として、防災の事業にも取 […]

津波災害の恐ろしさとその対策を語るとき、必ず出てくるのが「津波てんでんこ」の教え。 「てんでんこ」とは各自のことで、海岸で大きな揺れを感じる地震があったときは、必ず津波が来るから、各自はてんでんばらばらに一刻も早く高台に […]

富士川は、3,000m級の山々に囲まれて、長野県・山梨県・静岡県を流れ、流域の約90%が急峻な山地で、日本三大急流の一つに数えられている。特に、富士宮市の釜口峡は、最も川幅が狭まった場所で、激しい濁流により独特な岩肌が作 […]